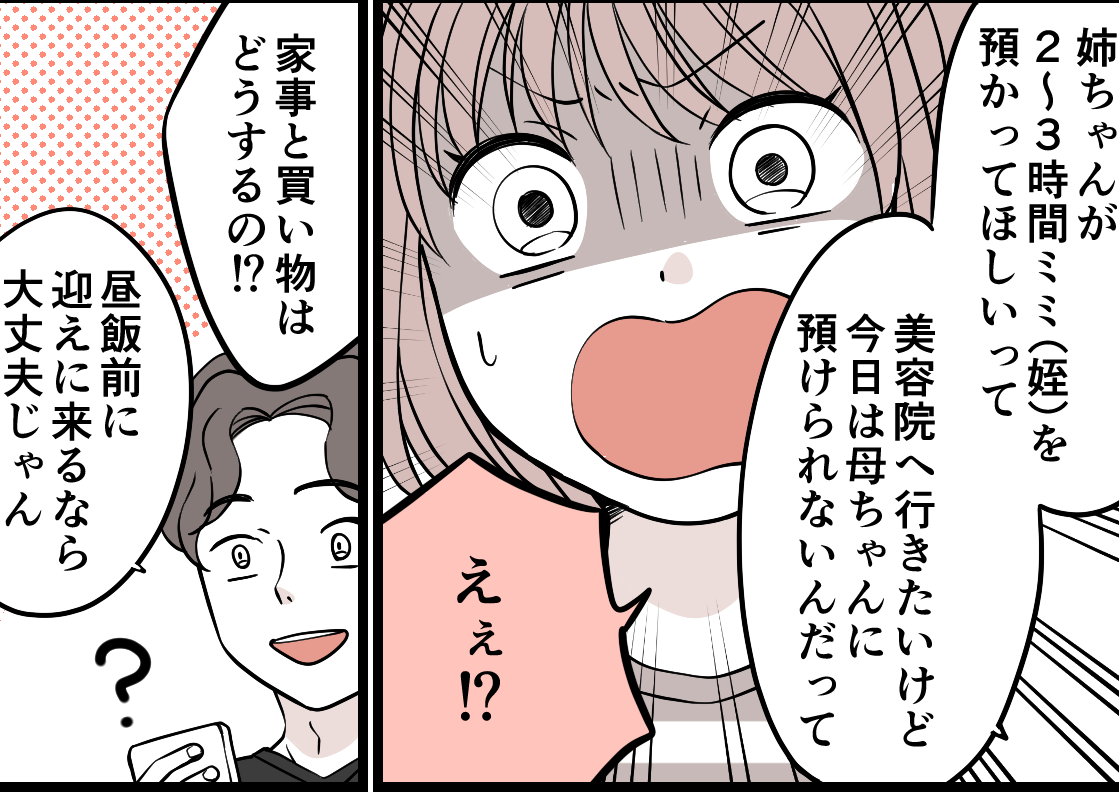「桃の節句」って何をすればいいの? #今さら聞けない基礎の基礎

ママたちも小さな頃から親しんできた行事の定番といえば、3月3日の「桃の節句」ではないでしょうか? 寒さがゆるみホッとできる気候、桃の花のピンク色、かわいいおひなさまなどハッピーなイメージが次々に浮かびます。でもどうして桃の節句におひなさまを飾るのか知っていますか?
新米ママパパに送る基礎知識、今回は「桃の節句」についてご紹介します。
「桃の節句」って、そもそも何の行事なの?
「節句」というのは、季節を分ける節目のこと。起源となった中国では奇数の数字が重なる日には災いが起きると考えられており、それを払うための祭りを行うことになったのだとか。5月5日は「端午の節句」、7月7日は「七夕の節句」、9月9日は「重陽の節句」、そして3月3日は「上巳(じょうし・じょうみ)の節句」です。「桃の節句」ではなく「上巳の節句」。3月最初の巳(み)の日を指し、これがいつしか3日に定まってきたそうです。
ひな祭りの元は草木や紙、わらなどの簡素なもので作った人形(ひとがた)に、自分の厄や災いを移し、川や海に流した「流しびな」の行事と、その後平安時代に始まったお人形遊び(ひいな遊び)と結びついたのが、現在の「ひな祭り」です。
「桃の節句」って、何をすればいいの?

「桃の節句」にはひな人形を飾り、みんなで祝い膳を食べるのが一般的です。とはいえ家庭ごとにアレンジしても、もちろんOK。「絶対にやらなくてはいけない」というものではありません。
ひな人形も立派なものがあれば越したことはありませんが、大切なのは「娘が幸せになりますように」と込める気持ちです。もしひな人形を持っていない家庭であれば、折り紙の手作りびなでも不足はないと思います。
お祝いの料理に使われる食材には、正月のおせちのように縁起をかついだものが多く使われています。
・はまぐり→他のハマグリの殻とは絶対に合わないことから、夫婦円満の象徴。将来よい伴侶と巡り合えるように、という願いから桃の節句ではお吸い物に使われるのが定番です。
・レンコン→見通しのいい人生を願う
・エビ→長寿祈願
・豆→健康勤勉を願う
これらの食材はちらし寿司に使われるのが定番です。ちょうど新鮮な魚介類が多く出回る季節なので、旬の味を楽しむのにもぴったりですね。
・ひなあられ→使われる四色(白・ピンク・黄色・緑)は四季を表す
ひなあられを炒っているときによく弾けると、その年はよいことが多いという言い伝えも! おひなさまにお供えしたあとで食べるのが、一般的です。
初節句の場合は何をすればいい?

女の子が生まれてはじめて迎える桃の節句が「初節句」です。
古くは嫁入り道具の一つとして婚家に送ったというならわしから、本来ひな人形はママの実家から贈られるもののよう。ただ、現代では両家が話し合って分担する、など家庭ごとにさまざまなパターンがあります。
初節句には「この子が健やかに育ちますように」と願いを込め、神社へお参りにいく家庭も少なくないようです。祈祷や祝詞(のりと)をお願いするならば、事前に神社に問い合わせをしておくと安心です。
その後は自宅で、桃の節句の祝いをします。出産から間もないのであればママの体調などを考慮して、外食にしたりデリバリーを頼んでおくのもよいでしょう。
また、本来は3月3日に行うお祝いごとですが、「宵節句(よいぜっく)」=前の晩に宴を開くのも悪くありません。
親戚などから初節句のお祝いをいだたいたのであれば、その祝いの席に招待します。これが「内祝い」の代わりになるので、品物などを用意する必要はありません。お招きするのが難しい場合は、いただいた額の半分ほどを目安にお菓子などを贈ります。本来はお祝いの手紙に赤飯や角砂糖を添えて送るものですが、現代ならその代わりに赤ちゃんの写真を添えるのもおすすめ。
「桃の節句」素朴な疑問あれこれ
Q.ひな人形を姉妹で共有してはいけない、というけれど?
たしかに本来は「ひとり飾り」であるため、姉妹で共有したり、親から受け継ぐのはよくないこととされています。ただ飾るスペースがないなど、現実的にはそうもいかない場合が多いよう。それぞれが小さな親王飾りのみにする、お姉ちゃんのときに買ったおひなさまに新しいお人形や飾りを足していく、などのやり方で対応してみては?
Q.ひな人形をすぐ片づけないと、お嫁に行きそびれる?
よくいわれることですが、根拠はもちろんありません。「おひなさまは春の飾りものだから、季節の節目にちゃんと片づけること」という、しつけの意味から来ている説もあるようです。
人気連載をイッキ読み!